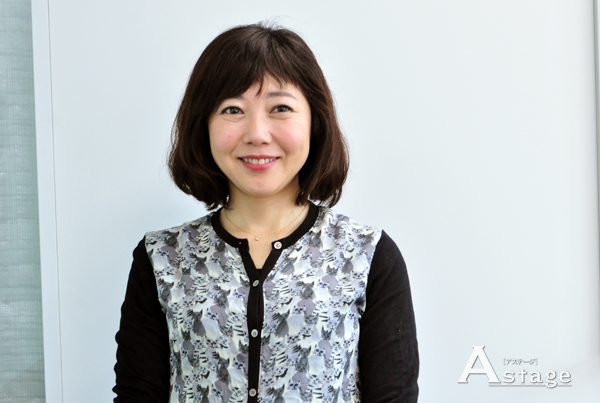
妻が死んだ。これっぽっちも泣けなかった。そこから愛しはじめた。
映画『永い言い訳』
『ゆれる』『ディア・ドクター』を手掛けた西川美和監督が、原作・脚本・監督をつとめた『永い言い訳』。不慮の事故で妻を失うが、その時不倫相手と密会していた人気作家の幸夫(本木雅弘)は、妻の死を悲しむこともできず涙も流せない。本作はそんな彼が同じ事故で母親を失った一家と出会い関わりを深めるうちに、初めて亡き妻や自分自身を見つめ直していく様を描く。優しさとは、愛とは・・・を問う感動のラブストーリーだ。
2016年10月に劇場公開され、国内外で高い評価を受けた本作のBlu-rayとDVDが発売されたことを記念し、西川美和監督にお話をうかがった。
― 映画が公開されるや大きな反響を呼んだ本作ですが、監督の手応えはいかがでしたか?
意外な人が意外な共感をするものだなと思いました。置かれている立場や見た目とか雰囲気は全然違うのに「すごく自分と幸夫が似ています」と。男性が身につまされて、痛々しい気持ちになる・・・という反応は想定内だったのですが、性別関係なく、たとえば専業主婦の方が「自分を幸夫だと思った」など、あらゆるところでそういう意見を聞きました。でもそれはとても嬉しい感想です。私は「よく男性のことをあんなに書けますね」と言ってもらうことがありますけど、実は男性特有の性格や性質を描きだそうという意識よりも「幸夫」に私自身を投影して書いたので観た人に性別を超えて“人間らしさ”を感じていただけるのは、とても嬉しかったです。
― だからこそ、観ていると物語に引き込まれていくのかもしれませんね。
そうですね。自分自身を省みるように痛みを共有しつつ、でも、なんとか再起してほしいとエールを送る気持ちで観てしまう。それは本木さんの力でもあるし、そして子供たちの力もあったと思います。

― 小説として完成し、その後映画化されたときに、いい意味での誤算はありましたか?
小説が出来上がった時点で、もう小説の中にあった世界観は捨てようと思っていました。映画というものは、絶対に小説のようにはならないから。小説は小説で完結させて、新しいものを作ろうと思って脚本作りを始めたので、その頃には小説と違うところがどこなのかも、もうわからなくなっていました。映画が完成して振り返ってみると、思った以上に小説と似ているなと思う部分があることが誤算かもしれませんね。
やはり、生身の俳優が入ってきて実際にある風景の中で撮っていると、小説と映画は良くも悪くも違うものになってしまうんです。でもそこで、上手くいかなかったとか、妥協したとか、手を打ったという発想になると、非常にマイナス思考になってしまう。けれども私一人では考えつかなかったことを、ほかの人たちから貰えるのが映画作りの特徴ですから、私が小説でイメージしていた「幸夫」という人物と本木さんは、スタート地点から違うので、そこに本木さんがもたらすものをいかにふんだんに盛り込んで、私が書いた「幸夫」以上の魅力を発揮してもらうかというところが映画では大事だと思っていました。
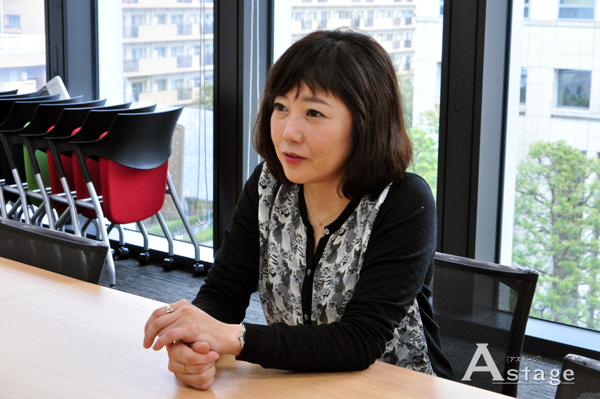
― 竹原ピストルさんの起用は、オーディションで決められたということですが?
そうですね。オーディションというより面談という感じでした。対座してお仕事ぶりなどを雑談するだけでしたが、部屋に入ってきた瞬間に、「この人だ!」と思いました。最初からとてもイメージに近かったんです、外見的にも。映ったときに画が強いから、セリフに頼らなくても色んなことが説明されるんですね。ピストルさんがトラックの中で(妻の残した)留守番電話を聞いて、カップラーメンをすすっているというだけでも、じゅうぶん彼が置かれている状況や心情が伝わってくる。それが映画ならではの強さですし、逆に会話をしているシーンでセリフが多くてカットしている部分もあるのですが(この部分は特典に入っています!)、彼ら俳優がそれぞれの人生で培った風貌や声質、話し方のトーンなどがこの映画を作ってくれているんだなと思います。

― では、本木さんをキャスティングされた理由は?
まず、本木さんがどんな方なのかよく知らなかったんです。あまり欠点が見当たらない雰囲気があり、人間味のないくらい完璧な50歳に見えてもいました。ただ、これまでの出演作品の中では、可笑しみのある作品を演られたものが私は好きで、二枚目が壁にぶち当たって七転八倒するような活劇的なものを書けたらいつかお声がけしてみたいなと昔から思っていたんです。今回の主人公は顔が良すぎる男で、その外見ゆえに人生がさらに歪んでいったという設定だったので、外見的にはピッタリ。でも、実際に会ってみると恐ろしくコンプレックスの塊だったんです。
― 本木さんがですか?
樹木希林さんやいろんな人から「面倒くさいですよ」と聞かされてはいたのですが、もう、想定を上回るほど。面倒くさいったらありゃしない(笑)。ひとつひとつにじっくり気の済むまで話をしたいし、悩んでしまうし、言い訳したいし、とにかく本人の葛藤が凄まじいんです。こっちはその自問自答に延々とつき合わなくてはならない。ひたすら手間のかかる方なんです(笑)。確かに面倒くさいけど、同時にとても人間的。本木さんがぐずぐず考えていることや抱えている悩みというものは、どこかしら自分にも思いあたる自信のなさであり人恋しさでありヒガミなんです。けっしてワガママではなく、人間的な煩悩と悩みの多い方なので、ついつい引き込まれていき、この人に付き合うしかないなと周りの人間全員に思わせる吸引力があるんです。「幸夫」とはまた少し違うんですが、外見からは想像もできないような内面的な葛藤を持っているという意味では、キャスティングを考えた時点よりも実際にお会いしてからのほうが「ああ、この人(幸夫に)近いな」と感じました。
― 確かに画面からも演技の深さを感じます。ところで、今作では子供たちとの関わりもクローズアップされていますね。
大人になりきれず、そのまま中年になってしまった男が、どういうことをきっかけに変化していくかという時、一番苦手なものをぶつけていこうと思ったんです。1つは陽一という人間。幸夫は、「小説」というような、いわゆる無形のものをこしらえて、見合わない評価を受けたり、華やかなところに出されたり・・・と、本当に自分自身の実態がなくなってしまったスノビッシュな作家。その対局的な人物として、陽一がいる。幸夫の調和を乱すトーンを持っていて、出会った時点で苦手意識が爆発しているのですが、さらにその子供という、予定調和を崩す存在を登場させました。
ただ、実際本木さんは3人のお子さんを育てていらっしゃっていて、なおかつロンドンではしっかりと育児にも専念されており、一方スタッフのほうは独身者が多く、子育ての経験がない人がほとんどでしたから、スタッフの手が回らなかったり、どうしていいか分からなくて天を仰いでいるときに、いつも本木さんが保父さんのように面倒を見てくれていました。本当に助かりました。

― なるほど。子供とのシーンは台本があったとは思えないような、とても自然な演技でした。
もちろん、台本はあったのですが、子供のシーンに関してはセリフを書いていない場面もけっこう多かったですね。決まったことを上手く演ってもらうことが目的ではなくて、私にも考えつかないような子供らしさをどれだけ切り取れるかというところが、前半のキーでもあったので、シチュエーションだけ考えて子供と本木さんに任せた場面もたくさんありました。そして、カメラが回ってないところの時間の中で子供と本木さん、子供とピストルさんがとても充実した過ごしかたをしてくださったので、それが素直に画に映っているなという感じがします。本木さんはご自身が子供に慣れているので、子供に不慣れであるはずの幸夫がこなれ過ぎて見えないか、ということをすごく気にされていました。
― 子供たちも本当の兄妹のように見えてきます。
そうですよね。でももちろん血はつながっていないんです。あの二人も、オーディションの頃から一緒にご飯を食べに行ったり、ボーリングをしたり、二人で過ごす時間を重ねていったのですが、彼らは大人以上に適応能力が高いので、毎日会っていなくてもまた会えば本当の兄妹のように言葉無しでもぴったり一緒に行動しているし、離れていれば「早く会いたい」というふうになっちゃう。そういう子供らしい順応性にも助けられました。
この映画は、子供の可愛らしさを強調したり、子供を使って観客を泣かせるというようなことを狙ったのではなく、もっと子供という存在自体の度し難さを描きたかったんです。彼らが親にとって宝であることには間違いないけれど、そんなに大人が思うほど都合のいい生き物じゃない。彼らがいることでいろんなことが狂いつつも、でも彼らがいるからより明るいんだというジレンマがある存在だと思ったんです。社会にとって子供がどういう存在であるかということを客観的に観察して、子供が持っている両義性をちゃんと書きたいと思っていたんです。撮影現場では、私たち自身が幸夫のように「もうどうしたらいいんだろう・・・」となってしまう、そういうことの連続でした。子供たちがケンカしたり、思うように幸夫のいうことを聞いてくれなかったりするシーンは、自分たちが一番手を焼いたところですが、いつ振り返っても懐かしいし、私自身も何度見ても好きなんです。それは子供が子供のままでいられるように整えてくれたスタッフや、カメラマン・山崎さんの力ではないかなと思っています。
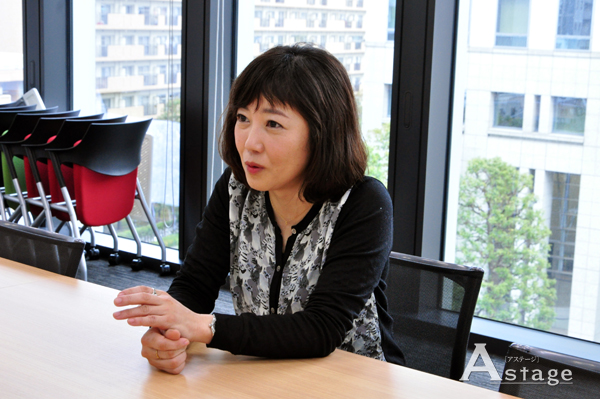
― 今回、16mmフィルムを使って撮影されたのはなぜですか?
私にとって、映画作りの原点回帰ですね。長い期間を使って撮ろうと思っていたので、予算的に大所帯では続かない。とにかく最小限のコンパクトなスタッフで乗り切らなければならない。機材が大きくなると人も増えるし、それだけ緊張感も高まるので、「子供がいい感じだね、今カメラを回しましょうか」というときに、すぐに回してくれるような環境ではなくなってしまう。全部の準備が整った頃には子供の鮮度が失せているというのが、普通の劇映画の現場なんです。今回は、大掛かりな打ち合わせをしなくてもフレキシブルに動けるというコンセプトを理解してくれるスタッフと仕事をしたかったんです。
私が映画界に入った90年代の後半は、インディペンデント映画のジャンルでスーパー16mmがよく使われていました。デジタルではなく、もう一度あの頃のように、自分の感覚を信じて、大きなモニターを出さなくてもいろんな人が第六感を使って「今だいたいこんなものが映っているんだろう」と、感覚を研ぎ澄ませながら映画作りに挑める環境に戻ってみたくて、スーパー16mmを選びました。そういう撮影環境に対応してくれるのが、長い間ドキュメンタリーを撮られてきた山崎さんであり、その周りのスタッフだと思ったんです。
そして、あまりにもデジタルが進化して、2~3年前にはフィルムが絶滅するのも時間の問題だ、などと言われてもいたので、ひょっとしたら私にとってはもうラストチャンスかもしれないなという気持ちもあって16mmフィルムを使って撮影しました。上映用にデジタル処理を加えるので、結果的には35mmのフィルム以上に粒子感などのフィルムらしさもわかりやすく出て、デジタルでは表し辛い曖昧な優しさのようなものがよく表現できたのではないかと思います。
― 普通の家庭でもホームビデオで撮ったことのあるような場面もありますね。
身近さみたいなものも感じられると思います。
― ところで、西川監督がオリジナル作品にこだわるのはどうしてですか?
話を書くというところが、私の一番の持ち場だと思っているんです。正直言って、映画は現場に入ればスタッフのみんながやってくれるんですよ(笑)。私はその責任を取るという立場ではあるけれど、やっぱり物語を作って構成して書くところは自分だけができることだと思っているので、そこをしっかりやっていないと、演出の責任を取る自信が持てないんです。なので、今回小説から書いたのも、しっかり自分に準備させるため。よく体をほぐして、さまざまに可動域を広げておいて、どういうふうに転んでも怪我しない身体をきちんと作った上で試合に臨めば大丈夫・・・という期間を長くしたというところでしょうか。
― 監督のこだわりが詰まった作品なんですね。
色々なところにこだわらせてもらったし、それに対して、みんながその世界観をとても大事にしてくれていました。美術のスタッフも小説をもの凄く読み込んでくれて、小説に書かれていたいものをさりげなく飾ってくれていたり、見えないところまでその空気を作ってくれました。

― そんな中で、監督が特にこだわったシーンや、印象深いシーンはありますか?
シーン毎に苦労したポイントは違いますが・・・、「あーちゃん(陽一の娘・灯)の誕生日パーティー」でしょうか。最初は和気あいあいと始まったかと思いきや、どんどん雲行きが怪しくなり、幸夫がいろんなものをぶちまけてぶち壊して帰っていくというシーンの展開は、とても大事なシーンでしたし、ここで本木さんがきちんと自分らしく良いお芝居をしてくれればこの映画はいける!と思っていました。本木さんは大変悩んでおられましたが、その大変悩んでいる様もメイキングにたっぷりと収まっています(笑)。
本木さんのアップのカットを現場で見ながら、「ああいけたな!この映画は」と確信しました。私は1本の映画の現場で1~2回そういう瞬間があればいいと思っているんです。俳優がこっちの想定をポンと超えるときというものがあって、それがあのシーンでした。私以上に、本木さん自身にとって良かったと思いましたし、とても良いシーンになったと思います。そして、どんどん変化していく本木さんを間近に見て、子供たちがどんな顔をするんだろうというところも、ポイントでした。リハーサルのときは子供を呼ばなかったんです。1回目のリアクションを撮りたくて。ですから、本木さんは直前まで人形を相手に芝居をしていたんですよ(笑)。
その頃になるとあーちゃんも随分場数をこなしてきて、自分がどうあるべきか、何をするべきなのかということが頭に入っていたので、お芝居の受け答えがもう“神ってる!”と思いましたね。実は、そのシーンは全部台本のセリフなんですが、書いたセリフに聞こえないような受け答えをしてくれている。夏の終わり頃の撮影だったのですが、いろんなものが熟してきて、全ての俳優たちがそれを上手く発揮してくれていました。
― 映画の内容はもちろん、特典も楽しみですね。
特典は、メイキング、未公開シーン、名場面集、劇中アニメ「ちゃぷちゃぷローリー」絵コンテ完尺版、そして、劇中では読まれなかった妻・夏子からの手紙(ライナーノーツ「ラブレター」)も入っています。夏子が旅行先に着いたら投函しようと思っていた手紙・・・湖に沈んだ妻からの手紙です。特典はBlu-ray限定ですので、是非!
Blu-ray&DVDは映画を見逃した方はもちろん、ご覧になった方にこそ、観ていただきたいです。

【西川美和(にしかわみわ)原作・脚本・監督 プロフィール】
1974年7月8日、広島県出身。早稲田大学第一文学部卒。大学在学中より是枝裕和監督の『ワンダフルライフ』(99)にスタッフとして参加。以後、フリーランスの助監督を経て、2002年に『蛇イチゴ』でオリジナル脚本・監督デビュー。第58回毎日映画コンクール・脚本賞ほか数々の映画新人賞を獲得。06年、長編第二作となる『ゆれる』がロングランヒット、第59回カンヌ国際映画祭監督週間に正式出品される。その後も09年『ディア・ドクター』、12年『夢売るふたり』など、国内外で賞賛を受ける。
また、映画界の活躍以外に小説・エッセイの執筆も手掛け、『ゆれる』のノベライズで第20回三島由紀夫賞候補、『ディア・ドクター』のアナザー・ストーリー「きのうの神様」で第141回直木賞候補、「永い言い訳」で第153回直木賞候補、2016年本屋大賞候補となった。その他「その日東京駅五時二十五分発」「映画にまつわるXについて」などがあり、一貫してオリジナルストーリーに挑み、その創作活動に熱い注目が集まっている。
映画『永い言い訳』は2016年に公開された。

映画『永い言い訳』
第71回毎日映画コンクール 監督賞(西川美和)受賞
第71回毎日映画コンクール 男優主演賞(本木雅弘)受賞
第90回キネマ旬報ベスト・テン 助演男優賞(竹原ピストル)受賞
第40回日本アカデミー賞 優秀助演男優賞(竹原ピストル)受賞
第26回日本批評家大賞 脚本賞(西川美和)受賞
<あらすじ>
妻を亡くした男と、母を亡くした子供たち。
その不思議な出会いから、「あたらしい家族」の物語が動きはじめる。
人気作家の津村啓こと衣笠幸夫(きぬがささちお)は、妻が旅先で不慮の事故に遭い、親友とともに亡くなったと知らせを 受ける。その時不倫相手と密会していた幸夫は、世間に対して悲劇の主人公を装うことしかできない。そんなある日、 妻の親友の遺族―トラック運転手の夫・陽一とその子供たちに出会った幸夫は、ふとした思いつきから幼い彼らの世話を買って出る。保育園に通う灯(あかり)と、妹の世話のため中学受験を諦めようとしていた兄の真平。子供を持たない幸夫は、 誰かのために生きる幸せを初めて知り、虚しかった毎日が輝き出すのだが・・・。
原作・脚本・監督:西川美和
出演:本木雅弘 竹原ピストル 池松壮亮 黒木華 山田真歩 深津絵里
製作:『永い言い訳』製作委員会(バンダイビジュアル株式会社、株式会社AOI Pro.、株式会社テレビ東京、アスミック・エース株式会社、株式会社文藝春秋、テレビ大阪株式会社)
原作:「永い言い訳」(文春文庫刊)
挿入歌:手嶌葵「オンブラ・マイ・フ」
©2016「永い言い訳」製作委員会
公式サイト:http://nagai-iiwake.com/
Twitter:https://twitter.com/nagai_iiwake @nagai_iiwake
Facebook:https://www.facebook.com/nagaiiiwake

『永い言い訳』Blu-ray&DVD発売中!
Blu-ray 限定特典●特典ディスク(DVD):メイキング、未公開シーン集、名場面集、劇中アニメ「ちゃぷちゃぷローリー」完尺版(アフレコ用線画シーン含む)
●ライナーノーツ「ラブレター」(著:西川美和)
Blu-ray・DVD 共通仕様●映像特典:特報、予告、TVスポット
●聴覚障害者対応日本語字幕付/英語字幕付(ON・OFF可能)
Blu-ray(BCXJ-1054)¥5,200(税抜)/DVD(BCBJ-4726)¥3,800(税抜)
発売・販売元:バンダイビジュアル株式会社
©2016「永い言い訳」製作委員会




















